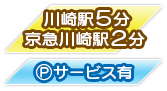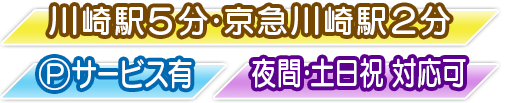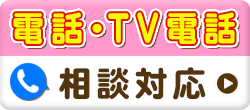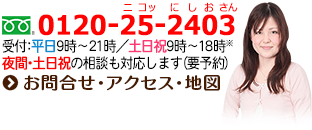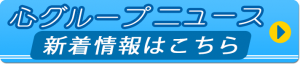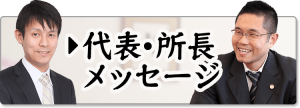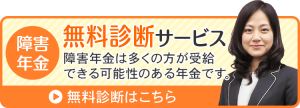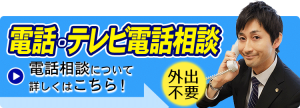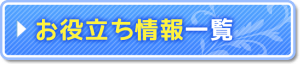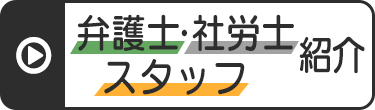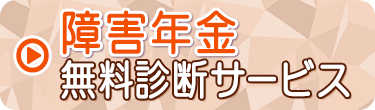障害年金を申請できる期間
1 障害年金を申請できるようになる日
⑴ 原則初診日から1年半が経過した時点から申請できる
病気やケガになって、すぐに障害年金を申請できるわけではありません。
例えば、交通事故で足の骨を折れば、事故直後は歩くこともできませんが、きちんと治療を受けて骨がきれいにくっつき、一定期間のリハビリをすれば、問題なく歩行が可能になることも珍しくありません。
このように、医学的に必要な治療を施せば障害が残らず完治する可能性もあるため、一定期間の治療をしてみて、それでも症状が残るものだけを、障害年金制度の対象とする必要があります。
障害の原因となった病気やケガについて初めて医療機関で診察を受けた日を初診日と呼び、障害年金では、原則として、初診日から1年半が経過した時点を障害認定日として、それ以降に申請が可能となる仕組みがとられています。
⑵ いくつかの特例
ただし、この1年半という期間は絶対のものではなく、いくつかの障害認定日の特例が設けられています。
例えば、人工肛門や心臓ペースメーカーを造設した場合、手足の切断等による欠損が生じた場合等には、1年半を待つ必要はなく、心臓ペースメーカーであれば手術日、手足の切断であれば切断した日、人工肛門であれば手術日から半年が経過した日等、特例による障害認定日を経過すれば障害年金の申請が可能になります。
2 20歳の誕生日以降になるのを待つ必要があります
知的障害で初診日が出生日となる方や初診日時点で20歳未満の方が障害基礎年金を請求する場合、20歳になるのを待つ必要があります。
ただし、20歳になるよりも初診日から1年半が経過するのが遅い場合は、初診日から1年半が経過するまで待つ必要があります。
なお、20歳になる前に就職して厚生年金制度に加入していた時期に初診日がある場合には、障害厚生年金については20歳になる前でも請求が可能です。
3 高齢になってからの申請について
⑴ 障害認定日での請求
障害年金を申請するためには、原則として初診日に公的年金制度に加入している必要があります。
国民年金の第1号被保険者(自営業、無職の方等)になれるのは60歳未満の方です。
第2号被保険者(サラリーマン、公務員等)になれるのは原則として65歳までの方です。
第3号被保険者になれるのは65歳未満の方です。
例外として、被保険者であったもので日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満期間に初診日がある場合は、障害年金の申請ができます。
そうすると、65歳以降に初診日がある場合については障害基礎年金の申請ができません。
なお、厚生年金の被保険者である場合には、障害基礎年金の申請はできませんが、障害厚生年金のみの申請はできます。
⑵ 事後重症での請求
また、障害年金の申請が可能になる障害認定日では障害の程度が軽かったなどの理由で障害年金を受給できなかった人が、その後、障害の程度が悪化したことを理由に、障害年金の請求する事後重症請求についても、65歳以降はできなくなってしまいます。